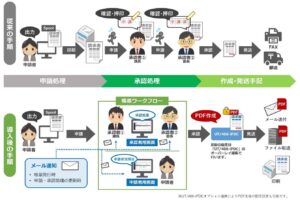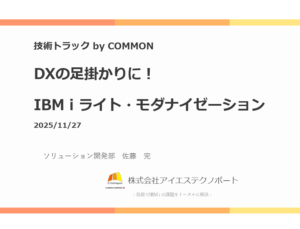日本IBM様では毎年、IBM iのユーザーやパートナーを米国ミネソタ州ロチェスターにあるIBMロチェスター研究所へお連れして、IBM i開発の第一線を見学してもらう視察ツアーを開催しています。
IBMロチェスター研究所は、IBM i開発の最大の拠点。そこを訪問してIBM iの開発メンバーから直接、最新技術や今後について説明してもらうことで、その後の仕事に役立ててもらおうというのがツアーの目的です。
当社では2年前から毎年、社員を1名派遣してきました。今回は3回目で、3人目の派遣。今回は9月7日(日)~12日(金)に開催され、IBM iパートナーの7社11名が参加しました。
今回参加したソリューション開発部 部長のT・Sは、ツアー全体の印象を次のように話します。
「毎日のように接しているIBM iの開発の現場は見るもの聞くものが新鮮で、大きな刺激を受けました。中でも印象的だったのは、開発の一線を担う人たちの並々ならぬ自信と熱気で、言葉では言い表せないほどの感銘を受けました。
そして、それらの人たちが我々の意見に耳を傾け、じっくりと話を聞いてくれる姿勢にも感銘し、IBM iがより一層身近に感じられました。
全体としては、私自身の仕事の方向性について大きな示唆が得られ、非常に有意義でした。また会社にとって、そして会社の人たちにとっても有益な情報もたくさん得られ、参加してよかったと考えています。私の仕事人生の中で、長く記憶に残るツアーになるだろうと感じています」
T・Sは、「IBM i Strategy and Roadmap」と題する基調講演を行ったスティーブ・ウィル氏(IBM i CTO)に、「IBM iの新機能の選定や方向性はどのような過程を経て決定されるのですか」という質問をしました。ウィル氏の回答は次のようであったと、T・Sは振り返ります。
この質問は、T・S自身が、当社の新製品の開発や既存製品の機能拡張で常に直面している課題で、それをウィル氏にぶつけたものでした。
「私たち開発チームは、IBM iのお客様にとって次に必要になるものを常に考えています。最初に検討の対象となるのはお客様からのご要望で、その中で優先順位を決めて取り組んでいます。またお客様から依頼や要望がなくても、今後のビジネスを加速させるテクノロジーがあれば、積極的に取り組んでいます。
AIのような従来からの価値観を覆すような革新的なテクノロジーが出てきた場合は、真に取り組むべきものは何か、IBMとして判断したうえで、IBM iへの適用を考えていきます」(ウィル氏)
今回のツアーでは、ウィル氏の基調講演のほか、IBM Power(ハードウェア)、HA/DR、セキュリティ、AI、アプリケーション開発、DB2 for i、SQLサービス、システム管理などのセッションや、ハードウェアの耐久試験を見学するラボツアーなどがあり、多彩なプログラムが組まれていました。
T・Sはその中で、AIとSQLに特に強い関心をもちました。
「生成AIについてはIBM watsonx Code Assistant for iというコード開発支援のツールが予定されているようですが、それとは別にデータベース関連や運用関連などでも生成AIを適用した新しい機能が紹介され、生成AIに真剣に取り組むべきことを痛感しました。
また、SQLがIBM iのさまざまなところで全面に出てきていることも実感でき、これからはSQLを軸に据えて考えていくべきことも感じました」
T・Sは帰国後、訪問したお客様に「SQLをもっと積極的に使っていきましょう」と、お伝えしているとのことです。



◎関連情報:システム構成作成担当者目線の「IBM i ロチェスター・スタディー・ツアー2025」報告(iWorld Web掲載記事)